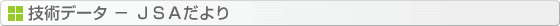 |
 |
| �ȃG�l�^���V�X�e���������i���Ƃ̓K�p���� |
|
| �����q�� |
�i��Ёj���V�X�e������u�t�c |
�i�������@2019�N 7�����j |
|
 |
| |
 |
|
1�D�͂��߂�
�@2015�N�̃p������iCOP21�j�̍̑��ɂ��A�䂪���̉������ʃK�X�r�o�ʂ̍팸�ڕW�́A2030�N�x�܂ł�2013�N�x��}�C�i�X26���A�����I�ɂ�2050�N�܂ł�80���Ƃ��Ă���B2017�N�x����l1�j�ɂ��ƁA�䂪���̉������ʃK�X�r�o�ʂ́A2013�N�x��}�C�i�X8.2���ł���A�ڕW�B���̂��߂ɂ͍X�Ȃ�w�͂��K�v�ł���B���ɂ����ẮA�p���������{�ݐ����v��i����30�N6���t�c����j�ŁA�ȃG�l���̓����ɂ�艷�����ʃK�X�팸�ʂ�5���g��CO2�i2017�N�x�����݁j����12���g��CO2�i2022�N�x�j�֊g�傷��ڕW�����Ă��Ă���B
�@���̖ڕW��B�����邽�߁A���Ȃł�2017�N�x���A�����̘V���������ݔ���p���āA�������@�B�ݔ������E���C���鎖�Ƃɂ��ĕ⏕�����{���Ă���B����́A2018�N�x�̓�_���Y�f�r�o�}���Ɣ�⏕���i�ȃG�l�^���V�X�e���������i���Ɓj��K�p��������iType2�j���Љ��B |
| |
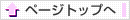 |
 |
�Q�D�⏕���Ƃ̊T�v
�@
�@ �⏕���Ƃɂ�2��ނ�����ȉ��ɊT�v�������B�⏕���Ƃ̗v���͔N�x�ɂ���������Ă���̂ŁA���Ƃ̌v��ɂ������Ă͍ŐV�ł��Q�Ƃ���K�v������B�Љ���2018�N�x�̎��Ƃ����A�����ł�2019�N�x�̊T�v���L�ڂ���B�Ȃ��A�⏕���Ƃ̎��s�c�̂́A��ʎВc�@�l�S�����c�̘A����������Ă���A�z�[���y�[�W�ɕ⏕���Ƃ̏ڍׂ��L�ڂ���Ă���2�j�B
�@Type1�@51�l���ȏ�̊��ݍ����������ɕt�т���@�B�ݔ����̉��C�E��������
�@�@�B�ݔ��̉��C�E�����ɂ���āA���Ƃ̑ΏۂƂȂ����@��̍��v�N�ԏ���d�͗ʂ��A���ƑO�ɔ䂵��5���ȏ�팸�ł��邱�ƁB
�AType2�@�\����Ɋ�Â��ݒu���ꂽ60�l���ȏ�̍������ɌW��{�̌�������
�@����12�N�i2000�N�j3�����܂łɐݒu���ꂽ60�l���ȏ�̊��ݍ������Ńu�������g�p������̂��A�ȃG�l�^�̍ŐV�����Ɍ������邱�Ƃɂ���āA�N�ԏ���d�͗ʂ�5���ȏ�팸�ł��邱�ƁB |
| |
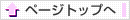 |
 |
�R�D�⏕����Type2�̓K�p����
�@
�@�Љ�鎖��͋����Z��̏��̌����ł���B�ߋ��ɏZ��̌��đւ����s���Ă���A���ݓ�������݂�Ƒ��ː����������Ă��邪�A���͊��݂����̂܂g�p���Ă����B����A���̘V�����ƈێ��Ǘ���̍팸�̂��߁A�⏕���Ƃ�Type2�𗘗p���ď��̌������s�����B
�i1�j�V�����̔�r
�@���ݏ��ƍX�V���̎d�l��\-1�Ɏ����B���ݏ��́A���a53�N�Ɍ��݂��ꂽ���\����^�̒����Ԃ��C�����iRC���j�ł���B���\����^�̒����Ԃ��C�����́A���ʒ������������A����������101�`2000�l����BOD60mg/L�A501�`5000�l����90mg/L�ł���B���{�݂́A���ʒ�������t�����A����BOD��20mg/L�Ƃ��Čv�悵�Ă����B�ʐ^-1�͍X�V����ݒu�����������̏ł���B��O�ɍX�V���iFRP���j�A���Ɋ��ݏ��iRC���j������A�����ǂ�؊�������Ɋ��ݏ���P�������i�ʐ^-2�j�B
 |
 |
| �ʐ^-1�@�X�V���ݒu�� |
�ʐ^-2�@���ݏ��P���� |
�i2�j��_���Y�f�r�o�̍팸����
�@���̓���ւ��ɂ��팸������_���Y�f�r�o�ʂ̎��Z���s�����i�\-2�j�B�@��̏���d�͔͂N�ԂŖ�40,000kwh�팸����A��_���Y�f�r�o�ʂ�20.4t��CO2���팸���ꂽ�B�܂��A1�N�Ԃ̕ێ�_����52��4��ɕύX����邽�߁A�ێ��Ǘ��Ŏg�p�����ԗ���蔭������CO2���啝�ɍ팸���ꂽ�B
| �\-2�@������ւ��ɂ��CO2�팸�� |
�i3�j���Ǘ��҂ɑ��郁���b�g
���̓���ւ��ɂ����Ǘ��҂ɂ͈ȉ��̃����b�g���������B
�@�y�n�̗L�����p
�@�@�\-1�Ɏ����悤�ɏ��̐ݒu�ʐς́A���ݏ��̖�70���ɍ팸���ꂽ�B
�@�@�܂��A�X�V���̏㕔�͒��ԏ�Ƃ��ė��p�ł���悤�Ȃ����B
�A�d�C�����̍팸
�@�@�d�C������20�~/kwh�Ɖ��肷���1�N�Ԃ������70���~�̍팸�ƂȂ����B
�B�ێ��Ǘ���p�̍팸
�@�@���ݏ��͏T1��̓_���ł��������A�X�V���4������1��ƂȂ邱�Ƃ���A
�@�@�ێ��Ǘ���p���啝�ɍ팸���ꂽ�B |
| |
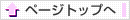 |
 |
�S�D���ݏ��̏�
�@
�@ �ߔN�A���x�������Ɍ��݂��ꂽ�R���N���[�g�\�����̘V�������Љ�I�ɖ��ƂȂ��Ă���B�����̓R���N���[�g�����̌��Ԃ֊O������C�̂�t�̂��Z�����A�l�X�ȉ��w�ω��╨���ω��������N�������ƂŌo�N���邽�߂ł���B����̊��ݏ��͒z40�N���o�߂��Ă���A���ݏ�����̂���O�ɁA��̂�ݔ����ǂ̂悤�ȏł��������������s�����B�������͑S����4.0m�i���C���̐��[��3.0m�j�Œn���0.8m�o�Ă��锼�n���\���ł���A�ׂ�RC���@�B�������݂���Ă���B
1�j������
�@�㕔�X���u�͍\���̂̏�Ɍ���50mm�̃����^���d�グ�i�d���ǂ̑ł����ݗp�j�ƂȂ��Ă���A�����^�������Œ���30cm�ȏ�̃N���b�N���A�J�������������Ɍ���ꂽ�i�ʐ^-3�j�B�������A���������̏��E�ǁE�V���J�������́A�N���b�N����^�����̏����E���ނ̘I�o�͖����A�O�ςɈُ�͌����Ȃ������B
�@���ʒ������Ƃ��C���̊Ԃ̕ǂɂ��ăR�A�������s���A�R���N���[�g���x�ƒ������������B�R���N���[�g���k�����̌��ʁA�R���N���[�g���x��35�m/mm2 �ł���v����x�ȏ�ł������B�R���N���[�g�̒����������ł́A���ʒ��������ŕ���7.4mm�i�ő�9.0mm�j���������i�s���Ă������A���C������0.0mm�ŁA�����̕��͋C�ɂ�蒆�����̐i�s�͈قȂ邱�Ƃ����������B���ɁA�����p���g�p����ꍇ�A���̒������������������ɂ�蔍�����A�R���N���[�g��C�����邱�ƂōX�Ȃ鉄����}�邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�@�}���z�[���i���S���j��ȍ|�W�iSS/�������b�L���j�A�������֍~���^���b�v�iSUS���j���������ɕ��A�͌���ꂸ�A�W�̊J�◬�����̏��~�Ɏx��͂Ȃ������i�ʐ^-4�j�B
2�j�@�B��
�@�@�B���̕ǂƓV��́A�h����Ƃ��ă��b�N�E�[���ɂ�鐁�t���s���Ă����i�ʐ^-5�j�B���a50�N�O��Ɏ{�H���ꂽ���b�N�E�[���̒��ɂ́A�����̂���A�X�x�X�g���܂�ł�����̂�����3�j���Ƃ���A��̂ɂ�����A�A�X�x�X�g�ܗL�̗L���ɂ��Ď������s���A�A�X�x�X�g���܂܂�Ă��Ȃ����Ƃ��m�F�����B�A�X�x�X�g�ܗL�̗L���͌����ڂł͔��ʂł��Ȃ����߁A�����̏�����̂��鎞�͒��ӂ��K�v�ł���B
3�j�ݔ�
�@�u������|���v���A���͋@��͒���I�ɍX�V����Ă���̏�@��͖��������B�����v�ʃ^���N�iFRP���j���X���u��ɐݒu����Ă������A�o�N�ɂ�����������K���X�@�ۂ������o�Ă����i�ʐ^-6�j�B�z�Ǘނ́A���O�̉��r�ǁA������SGP�ǂɗ�����ꂽ�B
 |
 |
| �ʐ^-3�@�㕔�X���u�ɔ��������N���b�N |
�ʐ^-4�@�J���W�̏� |
 |
 |
| �ʐ^-5�@�@�B�������̎d�グ�� |
�ʐ^-6�@FRP���^���N�̗� |
|
| |
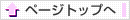 |
 |
�T�D������
�@
�@ ��ʂ�CO2��r�o����s�s��Ή����邱�Ƃ́ACO2�̌Œ�ƂƂ��Ƀq�[�g�A�C�����h����}�����A��炵�₷������n�o���邱�Ƃ���A�n�����g����Ƃ��čœK�Ȏ�@�ł���ƍl����B�������A���̎����̂��߂ɂ́A����Ȕ�p�ƍL��ȓy�n���K�v�ƂȂ邱�Ƃ���e�ՂłȂ��B
�@�Љ������ł́A���̓���ւ��ɂ��N��20.4t��CO2���팸�ł����B���̍팸�ʂ�2.3�w�N�^�[���̃X�M�l�H�тŋz������ʂɑ�������i1�w�N�^�[����40�N���̃X�M�l�H��1000�{��1�N�Ԃ�8.8����CO2���z��4�j�j�B�{���x�������̎{�݂Ŋ��p����ACO2�̍팸���i�݁A�n�����g���ɋN������C�ۍЊQ�������ł���������悤�ɂȂ�Ǝv���B
�Q�l����
|
| |
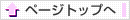 |
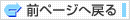 |